グルテンフリーとアレルギーの関係|違いや必要性を解説
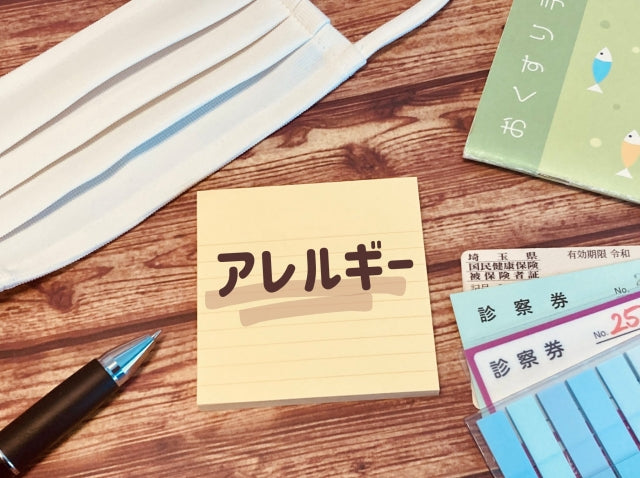
グルテンとは何か

グルテンの性質と含まれる食品
グルテンとは、小麦、大麦、ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種です。 グルテンは、小麦粉に水を加えてこねることで形成される粘り気のある物質で、パンやパスタなどの食品に独特の食感をもたらします。 小麦粉の主要なタンパク質であるグリアジンとグルテニンが結合することで、グルテンのネットワーク構造が形成されるのです。
グルテンは、小麦だけでなく、大麦やライ麦にも含まれています。 そのため、パン、パスタ、うどん、ケーキ、ピザ、ビールなど、これらの穀物を原料とする食品には、グルテンが含まれています。 また、グルテンは加工食品の添加物としても広く使用されており、ソース、ドレッシング、スープ、ハムなどにも含まれていることがあります。
グルテンの役割と加工食品への利用

グルテンは、パンやパスタなどの食品に欠かせない役割を果たしています。 グルテンのネットワーク構造が、パン生地の粘り気や弾力性を生み出し、パンを膨らませるのです。 また、パスタの歯ごたえやもちもち感も、グルテンによるものです。
グルテンは、食品の保形性、保水性、結着性を高める働きがあるため、加工食品の製造においても重要な役割を担っています。 ソースやドレッシングの粘度を調整したり、ハムやソーセージの結着性を高めたりするのに、グルテンが利用されるのです。 さらに、グルテンは、植物性タンパク質としても注目されています。 小麦グルテンを加工することで作られる小麦たんぱく(セイタン)は、肉の代替品として利用されることもあります。
グルテン関連疾患とは

セリアック病
症状と診断方法
セリアック病は、グルテンに対する免疫反応により、小腸の粘膜が損傷を受ける自己免疫性疾患です。 グルテンを摂取すると、慢性的な下痢、腹部膨満感、腹痛、体重減少などの消化器症状が現れます。 また、貧血、骨粗鬆症、成長障害、神経障害など、様々な合併症を引き起こすこともあります。 セリアック病の診断には、血液検査で特異的な自己抗体を調べることや、小腸の生検で粘膜の損傷を確認することが行われます。 症状や検査結果から総合的に判断されるのです。
グルテンフリー食の重要性
セリアック病の治療において、グルテンフリー食は非常に重要です。 グルテンを完全に除去することが、症状の改善と小腸粘膜の回復に不可欠なのです。 セリアック病患者は、生涯にわたってグルテンフリー食を継続する必要があります。 小麦、大麦、ライ麦など、グルテンを含む穀物由来の食品は、パン、パスタ、麺類、ケーキ、ビールなど多岐にわたります。
【セリアック病患者が避けるべき食品】
- パン、パスタ、ピザ、ケーキなどの小麦粉を使った食品
- うどん、そうめん、ラーメンなどの麺類
- ビール、麦茶などの大麦、ライ麦を使った飲料
- ソース、ドレッシング、スープなどのグルテンを含む加工食品
グルテンフリー食を実践するためには、これらの食品を避け、代わりに以下のような食品を選ぶことが大切です。
【セリアック病患者に適したグルテンフリー食品】
- 米、とうもろこし、そば、キノア、アマランサスなどのグルテンを含まない穀物
- 肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質源
- 野菜、果物
- ナッツ、種子類
- グルテンフリー表示のある加工食品
セリアック病患者がグルテンフリー食を守ることは、症状のコントロールと合併症の予防に欠かせません。 正しい知識を持ち、適切な食品選択を行うことが重要なのです。
小麦アレルギー

症状と診断方法
小麦アレルギーは、小麦に含まれるタンパク質に対する免疫反応により引き起こされる食物アレルギーの一種です。 小麦を摂取すると、じんましん、かゆみ、腹痛、嘔吐、下痢などの症状が現れます。
重症の場合は、アナフィラキシーショックを引き起こし、呼吸困難や血圧低下などの危険な症状につながることもあります。 小麦アレルギーの診断には、血液検査や皮膚テストで小麦特異的IgE抗体の有無を調べることが行われます。 また、食物経口負荷試験によって、小麦を実際に摂取した際の反応を確認することもあります。 症状や検査結果から総合的に判断されるのです。
原因物質と除去食
小麦アレルギーの原因となるのは、小麦に含まれるグルテンだけでなく、アルブミンやグロブリンなどの水溶性タンパク質も関与しています。 そのため、小麦アレルギー患者は、グルテンフリー食品であっても、小麦由来の原材料が使用されていないかを確認する必要があります。 小麦アレルギー患者が避けるべき食品は以下の通りです。
【小麦アレルギー患者が避けるべき食品】
- パン、パスタ、ピザ、ケーキなどの小麦粉を使った食品
- うどん、そうめん、ラーメンなどの小麦を使った麺類
- 小麦を含むシリアル、クラッカー、ビスケットなど
- 小麦を使った加工食品(ソース、ドレッシング、ルウ、スープなど)
- 小麦を含む飲料(ビール、発芽玄米飲料など)
小麦アレルギー患者は、これらの食品を避け、代わりに小麦を使っていない代替食品を選ぶことが大切です。 米、とうもろこし、そば、キノアなどの小麦以外の穀物や、小麦不使用の加工食品を活用するのがよいでしょう。
非セリアック性グルテン過敏症

症状と診断の難しさ
非セリアック性グルテン過敏症は、セリアック病や小麦アレルギーとは異なる機序で、グルテンに対する過敏反応を示す病態です。 グルテンを摂取すると、腹痛、腹部膨満感、下痢、便秘などの消化器症状や、頭痛、倦怠感、関節痛などの全身症状が現れます。 しかし、これらの症状は非特異的で、他の疾患でも見られることがあるため、診断が難しいのが特徴です。 非セリアック性グルテン過敏症の診断には、セリアック病や小麦アレルギーを除外し、グルテンフリー食による症状の改善を確認することが重要です。 しかし、明確な診断基準がないため、診断には慎重を要します。
グルテンフリーの効果
非セリアック性グルテン過敏症の治療は、グルテンフリー食が基本となります。 グルテンを除去することで、消化器症状や全身症状の改善が期待できます。 ただし、非セリアック性グルテン過敏症では、グルテンの完全除去が必須ではない場合もあります。 個々の患者の症状や感受性に応じて、グルテンの摂取量を調整することが大切です。
また、グルテンフリー食は、セリアック病患者ほど厳格である必要はありません。 小麦、大麦、ライ麦を避け、米、とうもろこし、そば、キノアなどのグルテンを含まない穀物を中心とした食事が推奨されます。 グルテンフリー表示のある加工食品を上手に活用することも有効でしょう。 非セリアック性グルテン過敏症の患者は、グルテンフリー食による症状の改善を実感しながら、自身に合った食事療法を見つけていくことが重要です。
グルテンフリーと小麦アレルギーの違い

原因物質の違い
グルテンとグリアジン
グルテンフリーは、主にセリアック病や非セリアック性グルテン過敏症の患者が対象となる食事療法です。 これらの疾患では、小麦、大麦、ライ麦に含まれるグルテンが問題となります。 グルテンは、グリアジンとグルテニンという2つのタンパク質が結合してできる複合体です。 特に、グリアジンがセリアック病や非セリアック性グルテン過敏症の症状に関与していると考えられています。 グルテンフリー食では、これらの穀物やグルテンを含む食品を避ける必要があります。
小麦の他の成分
一方、小麦アレルギーの原因となるのは、グルテン以外の小麦に含まれるタンパク質です。 小麦には、グルテン以外にも、アルブミン、グロブリン、グリアジンなどのタンパク質が含まれています。 小麦アレルギー患者は、これらのタンパク質に対して免疫反応を示します。 そのため、小麦アレルギー患者は、グルテンフリー食品であっても、小麦由来の原材料が使用されていないかを確認する必要があります。 グルテンを除去しただけでは、小麦アレルギーの症状を予防することはできないのです。
症状の違い
グルテンフリーが必要なセリアック病や非セリアック性グルテン過敏症と、小麦アレルギーでは、症状にも違いがあります。 セリアック病では、グルテンの摂取により小腸の粘膜が傷つき、慢性的な下痢、腹痛、体重減少などの消化器症状が現れます。 また、貧血、骨粗鬆症、神経障害など、全身性の合併症を引き起こすこともあります。
非セリアック性グルテン過敏症でも、グルテン摂取後に腹部不快感、下痢、便秘などの消化器症状や、頭痛、倦怠感、関節痛などの全身症状が見られます。 一方、小麦アレルギーでは、小麦摂取後にアレルギー反応が起こります。 じんましん、かゆみ、腹痛、嘔吐、下痢などの症状が急性に現れるのが特徴です。 重症の場合は、アナフィラキシーショックを引き起こし、呼吸困難や血圧低下など、生命に関わる症状につながることもあります。
このように、グルテンフリーが必要な疾患と小麦アレルギーでは、症状の種類や現れ方が異なります。 セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症では、慢性的な消化器症状や全身症状が主体となりますが、小麦アレルギーではアレルギー反応による急性の症状が特徴的です。 これらの違いを理解することは、適切な診断と治療を行う上で重要です。 症状からグルテンフリーが必要な疾患と小麦アレルギーを見分け、それぞれに応じた食事療法を実践することが求められるのです。
消化器症状とアレルギー症状
グルテンフリーが必要なセリアック病や非セリアック性グルテン過敏症では、グルテンの摂取により消化器症状が現れます。 慢性的な下痢、腹痛、腹部膨満感などが特徴的で、これらの症状はグルテンを除去することで改善します。
一方、小麦アレルギーでは、小麦タンパク質に対するアレルギー反応により、じんましん、かゆみ、口や喉の腫れなどの即時型アレルギー症状が現れます。 消化器症状として、腹痛、嘔吐、下痢なども見られますが、これらはアレルギー反応に伴う急性の症状です。
発症メカニズムの違い
グルテンフリーが必要な疾患と小麦アレルギーでは、発症のメカニズムが異なります。 セリアック病では、グルテンに対する自己免疫反応により小腸の粘膜が傷つき、炎症が起こります。 非セリアック性グルテン過敏症の発症機序は完全には解明されていませんが、グルテンに対する免疫反応や腸内細菌叢の変化などが関与していると考えられています。
これに対し、小麦アレルギーでは、小麦タンパク質に対するIgE抗体が関与する即時型アレルギー反応が主体となります。 小麦タンパク質を異物と認識した免疫システムが、IgE抗体を産生し、これが肥満細胞に結合することでヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、アレルギー症状が引き起こされるのです。
診断と治療法の違い

除去食の範囲
グルテンフリーが必要な疾患と小麦アレルギーでは、診断方法と治療法にも違いがあります。 セリアック病の診断には、血液検査で自己抗体を調べることや、小腸生検で粘膜の傷害を確認することが行われます。 非セリアック性グルテン過敏症の診断は、セリアック病や小麦アレルギーを除外し、グルテンフリー食による症状の改善を確認することが重要です。 これらの疾患の治療は、グルテンフリー食が基本となります。
小麦、大麦、ライ麦など、グルテンを含む穀物を除去することが必要です。 一方、小麦アレルギーの診断には、血液検査や皮膚テストで小麦特異的IgE抗体を調べることや、食物経口負荷試験が行われます。 治療は、小麦除去食が中心となります。 ただし、小麦アレルギーでは、グルテンだけでなく、小麦に含まれる他のタンパク質も除去する必要があります。 グルテンフリー食品であっても、小麦由来の原材料が使用されていないかを確認することが大切です。
経口免疫療法の適用
小麦アレルギーでは、経口免疫療法が治療選択肢の一つとして考えられています。 これは、小麦タンパク質を少量から徐々に増量して摂取することで、免疫寛容を誘導する治療法です。 小麦アレルギーの患者の中には、経口免疫療法により小麦の摂取が可能になる例もあります。 ただし、経口免疫療法はアレルギー反応のリスクを伴うため、専門医の管理下で行う必要があります。
一方、セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症では、現時点で経口免疫療法の有効性は確立していません。 これらの疾患では、グルテンフリー食が唯一の治療法であり、生涯にわたって継続することが求められます。 このように、グルテンフリーが必要な疾患と小麦アレルギーでは、診断方法や治療アプローチが異なります。 それぞれの病態に応じた適切な診断と治療を行うことが重要なのです。
グルテンフリー食品が必要な人

セリアック病患者
グルテンフリー食品が必要な代表的な疾患が、セリアック病です。 セリアック病は、グルテンに対する自己免疫反応により小腸の粘膜が傷つく慢性的な消化器疾患です。 グルテンを摂取すると、下痢、腹痛、体重減少などの症状が現れ、放置すると成長障害や貧血、骨粗鬆症などの合併症を引き起こします。
セリアック病の治療は、生涯にわたるグルテンフリー食が基本となります。 小麦、大麦、ライ麦などグルテンを含む穀物やそれらを原材料とする食品を徹底的に除去する必要があります。 セリアック病患者にとって、グルテンフリー食品は欠かせない存在であり、症状のコントロールと合併症の予防に不可欠なのです。
最近では、グルテンフリー食品の選択肢が増え、パン、パスタ、クッキーなど、様々な代替食品が利用できるようになっています。 しかし、グルテンフリー食品は一般的な食品と比べて価格が高いことが多く、経済的な負担も大きな問題の一つです。 セリアック病患者が安心して生活するためには、グルテンフリー食品の普及と価格の適正化が望まれます。
非セリアック性グルテン過敏症の人
セリアック病以外にも、非セリアック性グルテン過敏症の人もグルテンフリー食品が必要です。 非セリアック性グルテン過敏症は、セリアック病や小麦アレルギーとは異なる機序で、グルテンに対する過敏反応を示す病態です。 グルテンを摂取すると、腹部不快感、下痢、便秘などの消化器症状や、頭痛、倦怠感、関節痛などの全身症状が現れます。
非セリアック性グルテン過敏症の診断は、セリアック病や小麦アレルギーを除外し、グルテンフリー食による症状の改善を確認することが重要です。 治療の基本は、グルテンフリー食です。 ただし、非セリアック性グルテン過敏症の場合、グルテンの摂取量に個人差があり、完全なグルテン除去が必須ではない場合もあります。
症状の程度に応じて、グルテンの摂取量を調整することが大切です。 グルテンフリー食品は、非セリアック性グルテン過敏症の人の症状改善に役立ちます。 小麦、大麦、ライ麦を避け、米、とうもろこし、そば、キノアなどのグルテンを含まない穀物を中心とした食事に、グルテンフリー食品を取り入れることで、バランスの取れた食生活を送ることができるのです。
グルテンフリーの効果を実感している人

セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症と診断されていなくても、グルテンフリー食の効果を実感している人もいます。 グルテンを控えることで、消化器症状が改善したり、体調が良くなったりする例が報告されています。 また、グルテンフリー食は、健康志向の高まりとともに、ダイエットや美容、アスリートのコンディショニングなどにも注目されています。 グルテンを控えることで、腸内環境が整ったり、炎症が抑えられたりする可能性が指摘されているのです。
ただし、グルテンフリー食が健康に良いという科学的なエビデンスは十分ではありません。 グルテンフリー食品は、必ずしも栄養バランスに優れているとは限らず、過剰な糖質や脂質、添加物が含まれている場合もあります。 安易なグルテンフリー食品の利用は、かえって健康を損なう恐れがあるのです。 グルテンフリーの効果を実感している人は、自身の体調と相談しながら、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
グルテンフリー食品は、あくまでも食事の選択肢の一つとして、適切に活用することが求められます。 セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症の診断がある人はもちろん、グルテンフリーの効果を実感している人にとっても、グルテンフリー食品は重要な役割を果たしています。 しかし、グルテンフリー食品が必要かどうかは、個人の健康状態によって異なります。 自己判断で安易にグルテンフリー食品を取り入れるのではなく、医療機関での適切な診断と指導に基づいて、グルテンフリー食を実践することが肝要なのです。
グルテンフリー食品の選び方

表示の確認と注意点
グルテンフリー食品を選ぶ際は、表示の確認が非常に重要です。 日本では、食品表示法により、小麦、大麦、ライ麦など、グルテンを含む穀物は特定原材料に指定され、これらを原材料として使用している場合は、表示が義務付けられています。 まず、商品パッケージの原材料表示を見て、小麦、大麦、ライ麦などが含まれていないことを確認しましょう。
また、「グルテンフリー」や「グルテン不使用」などの表示がある商品を選ぶのも一つの方法です。 ただし、日本では「グルテンフリー」の表示基準が明確に定められていないため、表示だけを頼りにするのは危険です。 海外では、グルテン含有量が20ppm(parts per million)以下の食品を「グルテンフリー」と表示できると定められている国もありますが、日本にはその基準がありません。
そのため、「グルテンフリー」と表示されていても、微量のグルテンが含まれている可能性があるのです。 特に、セリアック病患者は、微量のグルテンでも症状が出ることがあるため、表示の確認には細心の注意が必要です。 原材料表示や製造工程、製造ラインなどの情報を詳しく調べ、確実にグルテンフリーの商品を選ぶことが大切なのです。
クロスコンタミネーションへの配慮
グルテンフリー食品を選ぶ際は、クロスコンタミネーション(交差汚染)にも注意が必要です。 クロスコンタミネーションとは、製造工程で意図せずにグルテンが混入してしまうことを指します。 例えば、グルテンを含む食品とグルテンフリー食品を同じ製造ラインで製造している場合、機械や器具を共有することで、グルテンが混入する可能性があります。
また、原材料の保管や輸送の際にも、グルテンを含む食品と混在することでクロスコンタミネーションが起こり得ます。 セリアック病患者など、微量のグルテンでも症状が出る人は、クロスコンタミネーションに細心の注意を払う必要があります。 「グルテンフリー」と表示されていても、製造工程でグルテンが混入するリスクがあるのです。
クロスコンタミネーションを避けるためには、専用の製造ラインで製造された商品を選ぶことが重要です。 「専用工場で製造」「専用ラインで製造」などの表示がある商品は、クロスコンタミネーションのリスクが低いと言えるでしょう。 また、信頼できるメーカーや販売店から購入することも大切です。 グルテンフリー食品を専門に扱うメーカーや販売店では、クロスコンタミネーション防止への取り組みが徹底されていることが多いのです。
バランスの取れた食事の重要性

グルテンフリー食品を選ぶ際は、栄養バランスにも配慮することが大切です。 グルテンフリー食品は、小麦粉の代わりに米粉、とうもろこし粉、そば粉などを使用することが多いのですが、これらの原材料は必ずしも栄養バランスに優れているとは限りません。 例えば、精製された米粉やとうもろこし粉は、ビタミンやミネラル、食物繊維が少ない傾向にあります。 また、グルテンフリー食品は、パンやパスタなどの主食だけでなく、菓子類やスナック類も多く存在します。
これらの加工食品は、糖質や脂質が多く、カロリーも高い傾向にあります。 グルテンフリー食品に偏った食事は、栄養バランスを崩し、健康を損なう恐れがあるのです。 グルテンフリー食品を選ぶ際は、原材料や栄養成分表示をよく確認し、バランスの取れた食品を選ぶことが重要です。 また、グルテンフリー食品だけに頼るのではなく、自然食品を中心とした食事を心がけることも大切です。
米、とうもろこし、そば、キノアなどのグルテンを含まない穀物や、野菜、果物、肉、魚、豆類などを組み合わせることで、栄養バランスの取れた食事が実現できるのです。 グルテンフリー食品は、あくまでも食事の選択肢の一つとして、適切に活用することが求められます。 バランスの取れた食事を心がけ、必要に応じてグルテンフリー食品を上手に取り入れることが、健康的なグルテンフリーライフを送るための鍵となるのです。
こめこのパレットのグルテンフリーメニューの紹介
グルテンフリーの米粉パン

こめこのパレットでは、小麦を使わない米粉100%のパンを提供しています。 米粉特有のもっちりとした食感と、小麦パンにはない優しい甘みが特徴です。 グルテンを避けたい方だけでなく、健康志向の方にもおすすめの商品です。 また、完全無添加にこだわり、安心・安全にも配慮しています。 小麦アレルギーの方や、グルテンフリーの食事を必要とする方にも、美味しいパンを楽しんでいただけます。
グルテンフリーの米粉ベーグル

米粉を使ったグルテンフリーのベーグルも人気商品の一つです。 もっちりとした独特の食感と、プレーンからフルーツ味まで様々な味のバリエーションが魅力です。 ベーグルサンドにしても美味しく、食べ応えのある満足感が得られます。 パレットのベーグルは、白砂糖を使わずてんさい糖を使用しているため、上品な甘さに仕上がっています。 ヘルシーなのに味わい深い、新感覚のベーグルをぜひお試しください。
グルテンフリーの米粉餃子

こめこのパレットでは、グルテンフリーの餃子も販売しています。 米粉を使用した生地は、小麦粉の餃子の皮よりもモチモチとした食感が特徴です。 具材の旨味を引き立てる、優しい味わいの皮に仕上がっています。 グルテンフリーの餃子は、市販品ではなかなか手に入りにくいアイテムです。 パレットの米粉餃子の皮があれば、グルテンを気にせず餃子が楽しめます。 自宅で手作り餃子を楽しむのにもぴったりの商品です。
グルテンフリーの米粉団子

米粉を使った、グルテンフリーの団子もパレットの人気商品です。 米粉ならではの、もっちりとした食感と優しい甘さが魅力です。
ヘルシーなおやつタイムを楽しみたい方におすすめの一品です。 小麦アレルギーの方や、グルテンを避けている方にも安心して召し上がっていただけます。
まとめ|グルテンフリーとアレルギーの正しい理解を
グルテンフリーとアレルギーについて理解を深めることは、自分自身や身近な人の健康を守る上で非常に重要です。 本記事では、グルテンの性質や役割、グルテン関連疾患の特徴、グルテンフリーと小麦アレルギーの違い、グルテンフリー食品の選び方などについて詳しく解説してきました。 グルテンは、小麦、大麦、ライ麦など特定の穀物に含まれるタンパク質で、パンやパスタなどの食品に独特の食感をもたらす重要な成分です。
しかし、セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症などのグルテン関連疾患では、グルテンの摂取が健康に悪影響を及ぼします。 これらの疾患では、グルテンフリー食が治療の基本となります。 一方、小麦アレルギーは、グルテンだけでなく小麦に含まれる他のタンパク質に対する免疫反応によって引き起こされます。 グルテンフリー食品が小麦アレルギーに対応しているとは限らないことを理解しておくことが大切です。
グルテンフリー食品を選ぶ際は、表示の確認とクロスコンタミネーションへの配慮が欠かせません。 さらに、グルテンフリー食品だけに頼るのではなく、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。 グルテンフリーやアレルギーに関する正しい知識を持つことで、適切な食事療法を実践し、健康的な生活を送ることができるのです。 セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症、小麦アレルギーなどの疾患は、一人一人症状や重症度が異なります。 自己判断で食事療法を始めるのではなく、医療機関での診断と指導に基づいて、適切な対応を行うことが大切です。
また、グルテンフリー食が必要な人やアレルギーを持つ人が、安心して外食やお買い物ができる環境づくりも重要な課題です。 飲食店や食品メーカーには、グルテンフリーやアレルギー対応への理解を深め、適切な商品やメニューの提供、情報開示が求められます。 さらに、社会全体でグルテンフリーやアレルギーに対する理解を深め、支援の輪を広げていくことが必要不可欠です。
学校、職場、地域コミュニティなどにおいて、グルテンフリーやアレルギーに関する正しい知識を共有し、理解と配慮を促進することが大切なのです。 グルテンフリーとアレルギーについて正しく理解し、一人一人に合った食事療法を実践すること、そして社会全体で理解と支援の輪を広げていくこと。 それが、グルテンフリーやアレルギーとともに生きる人々が、健康で安心な生活を送るための鍵となるでしょう。 本記事が、グルテンフリーとアレルギーについての理解を深め、適切な対応を行う一助となれば幸いです。













